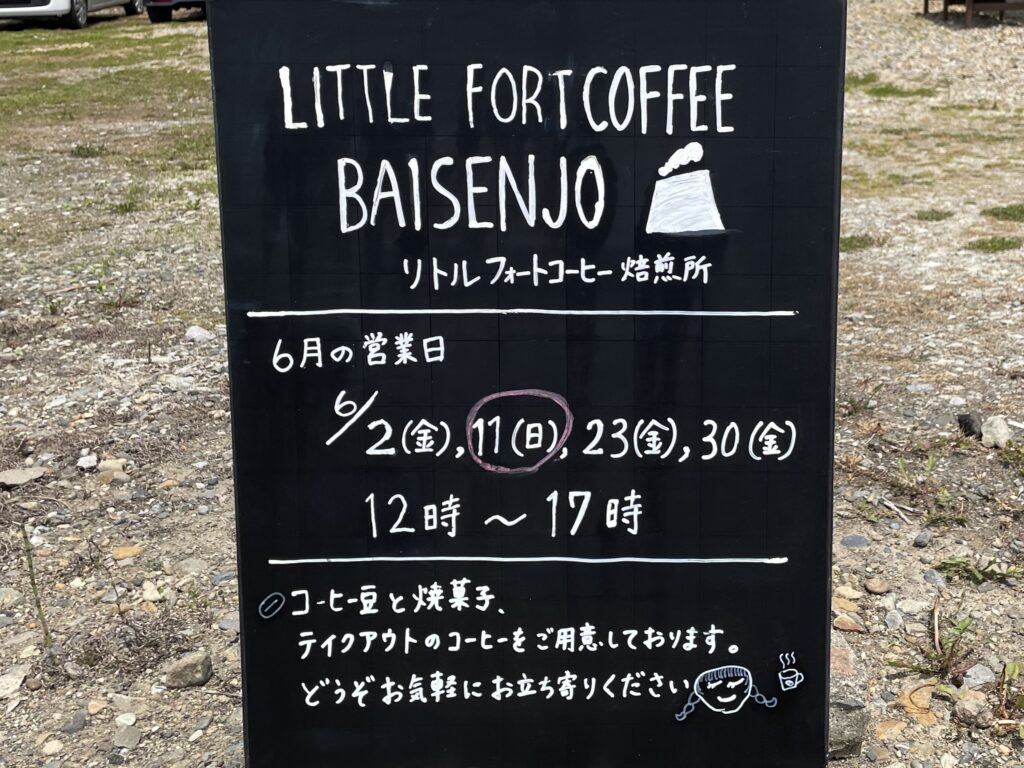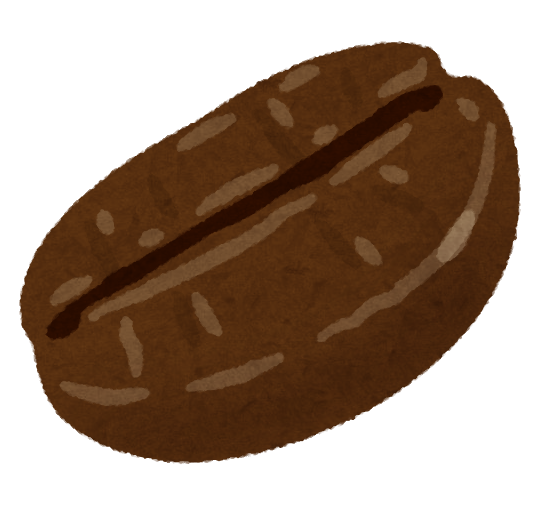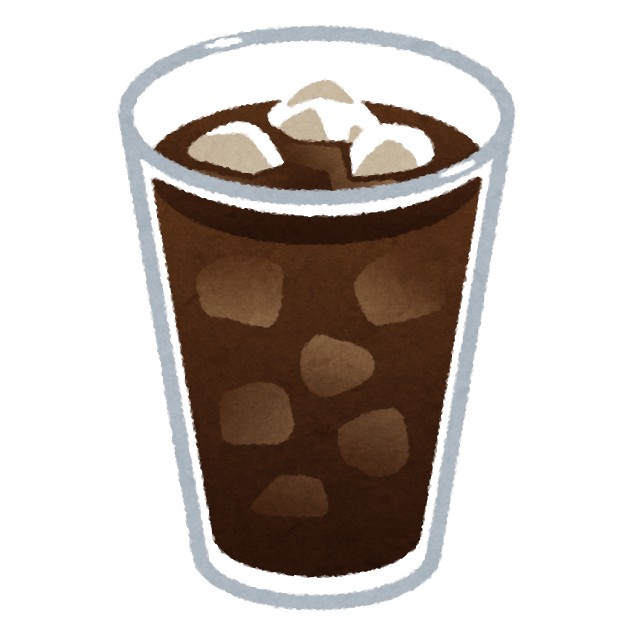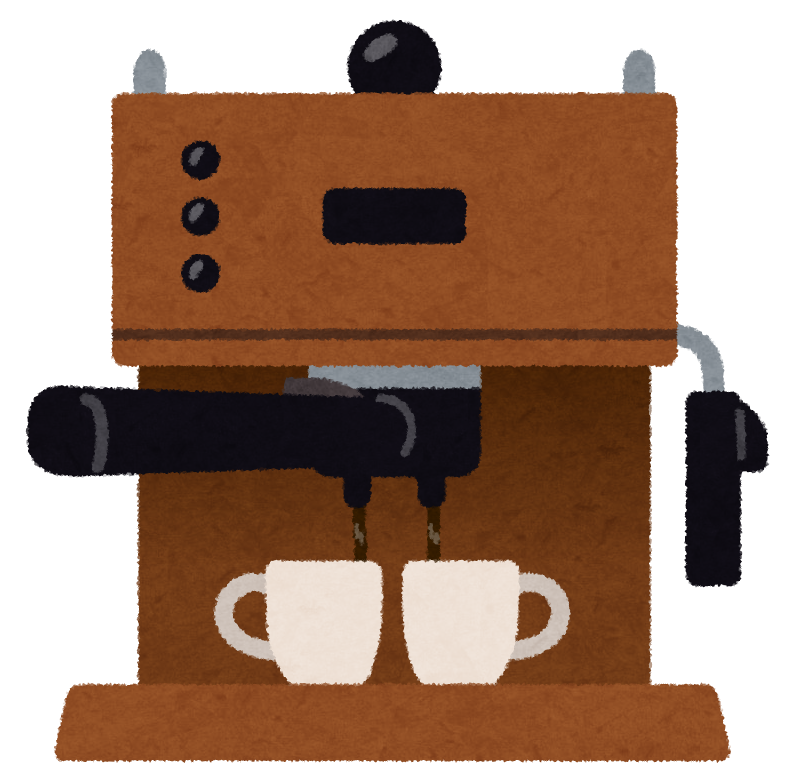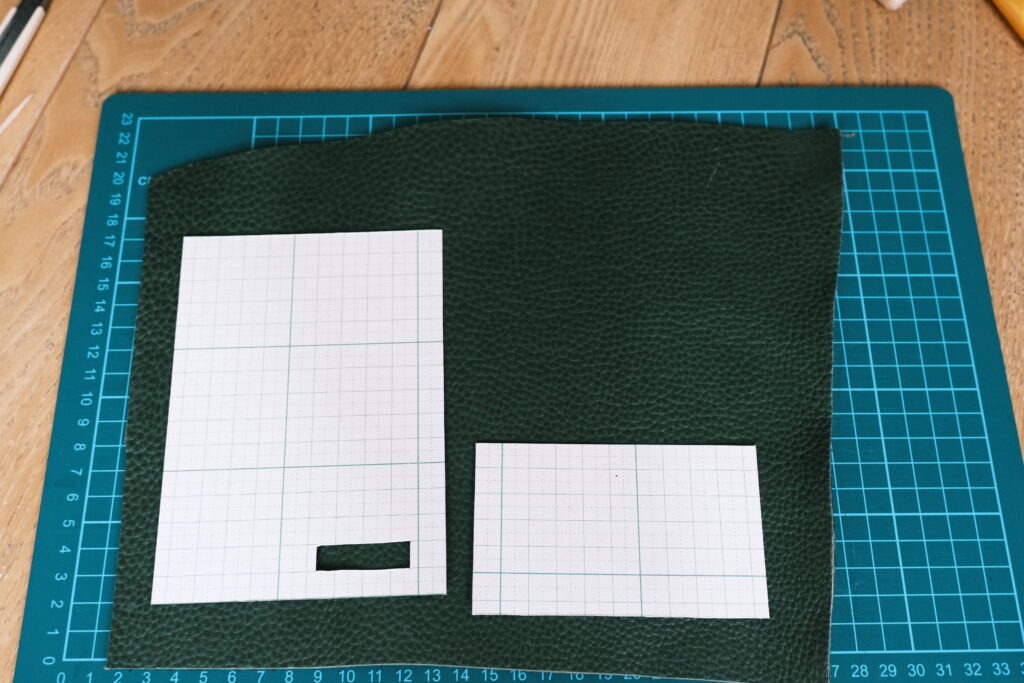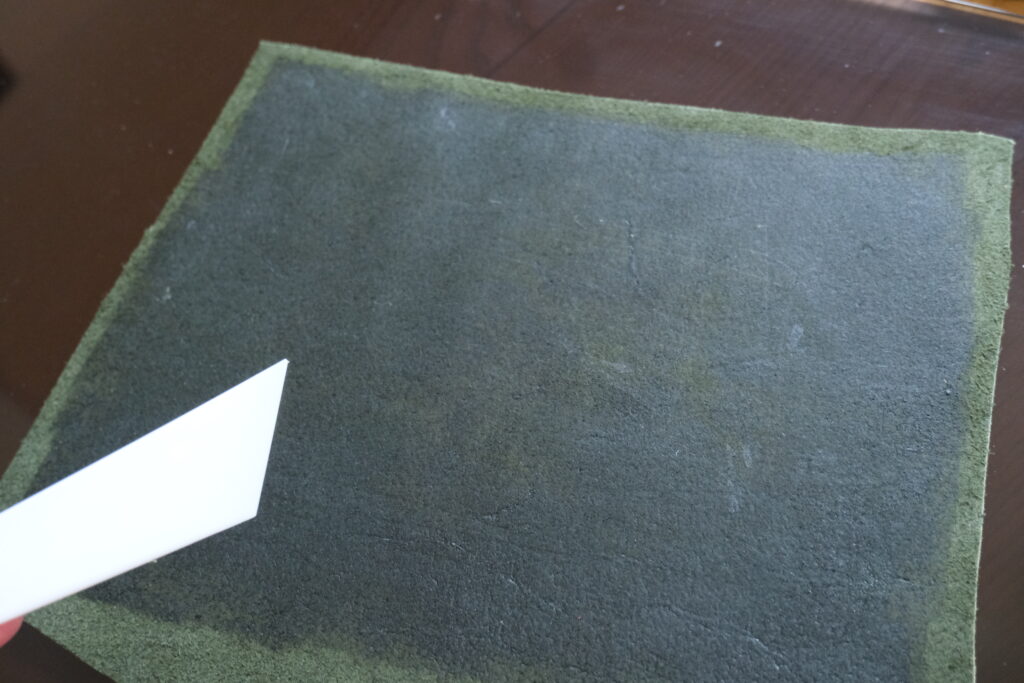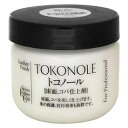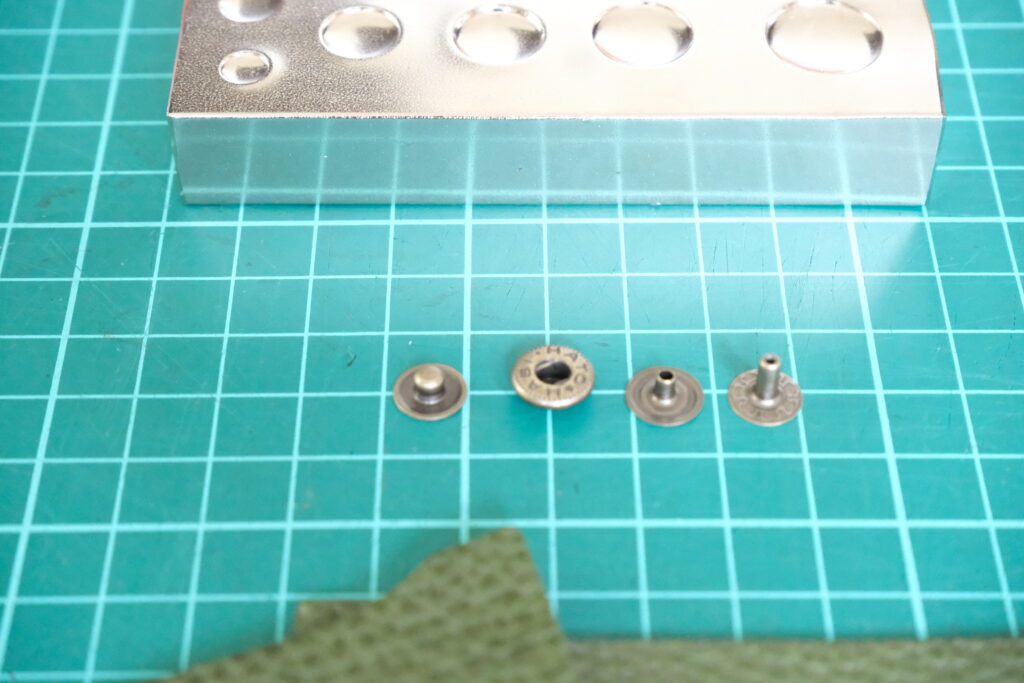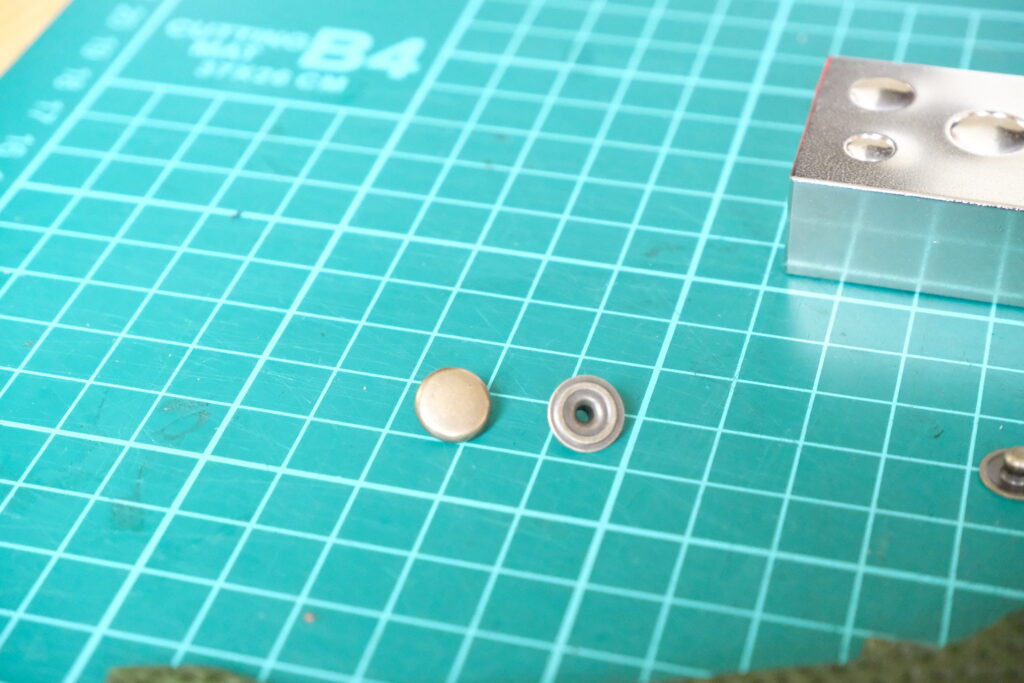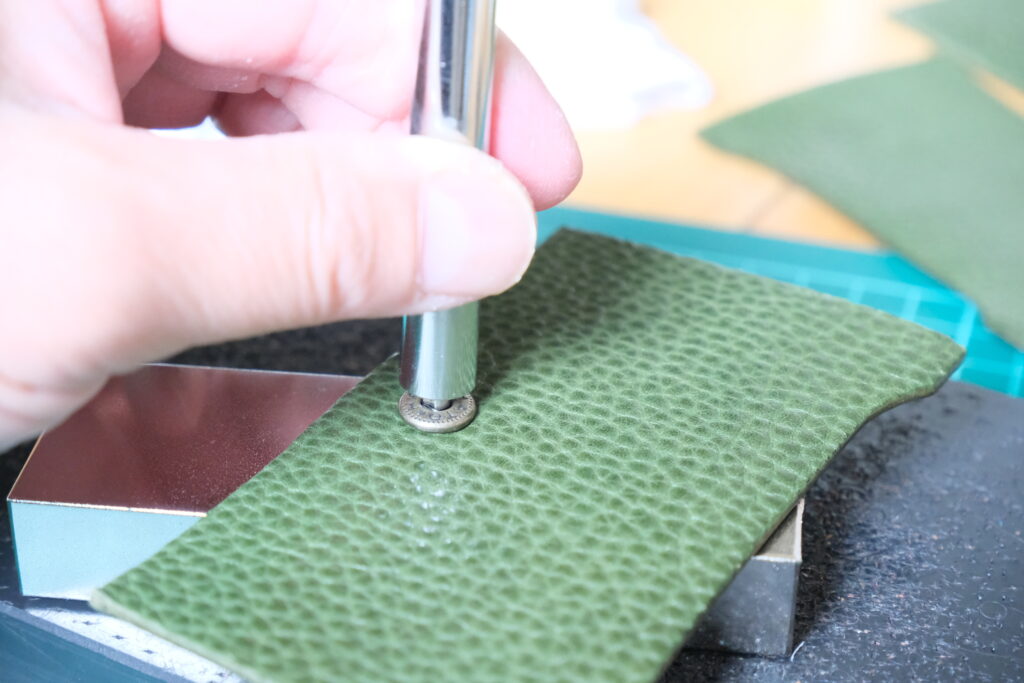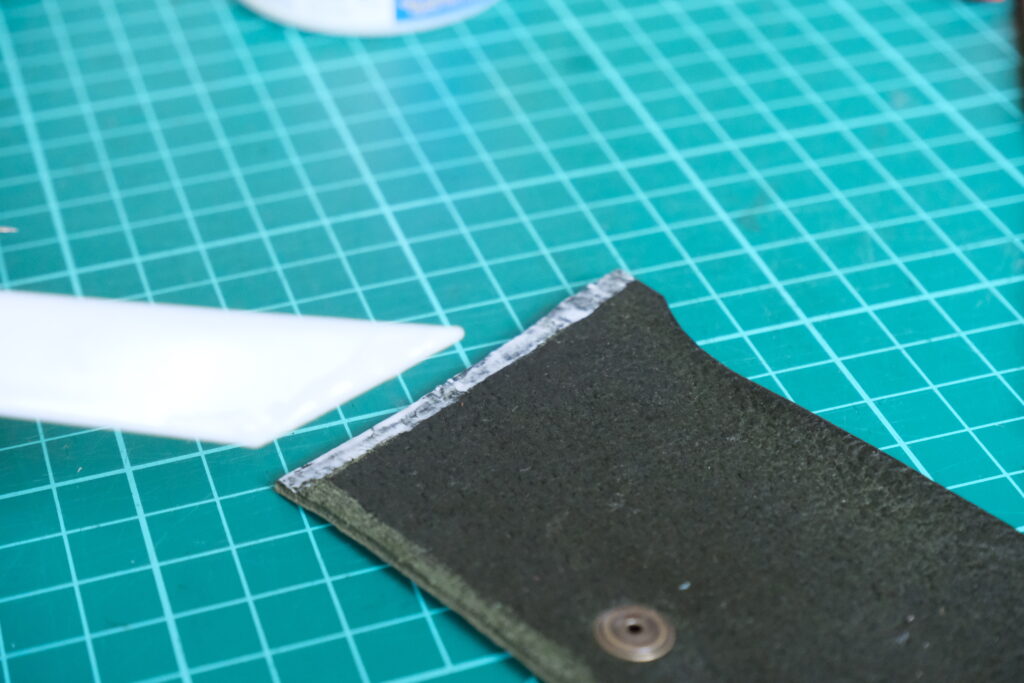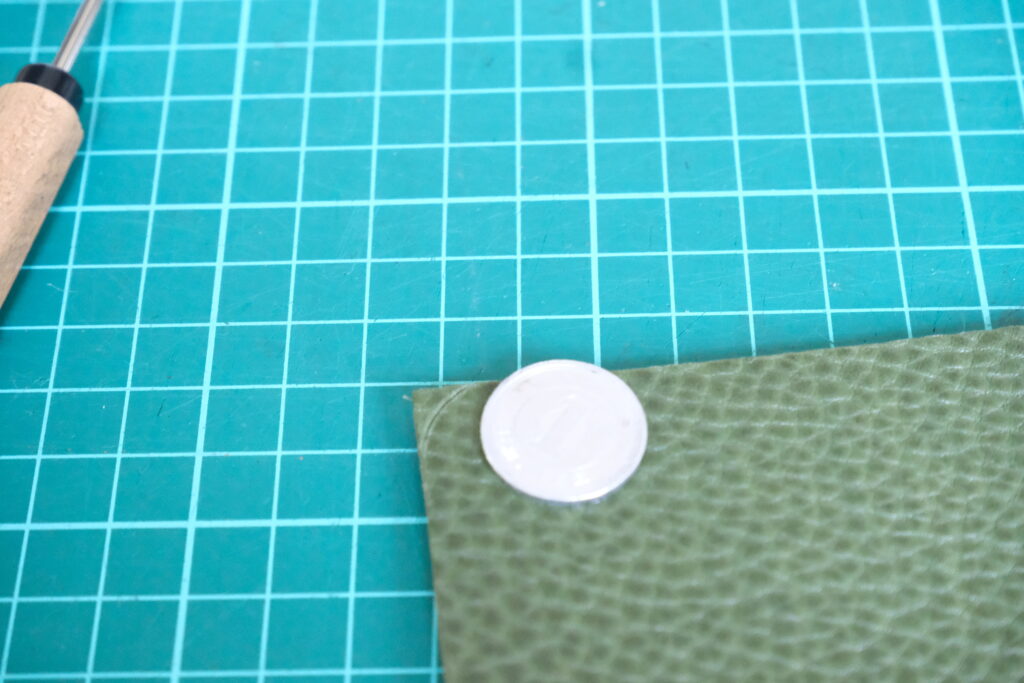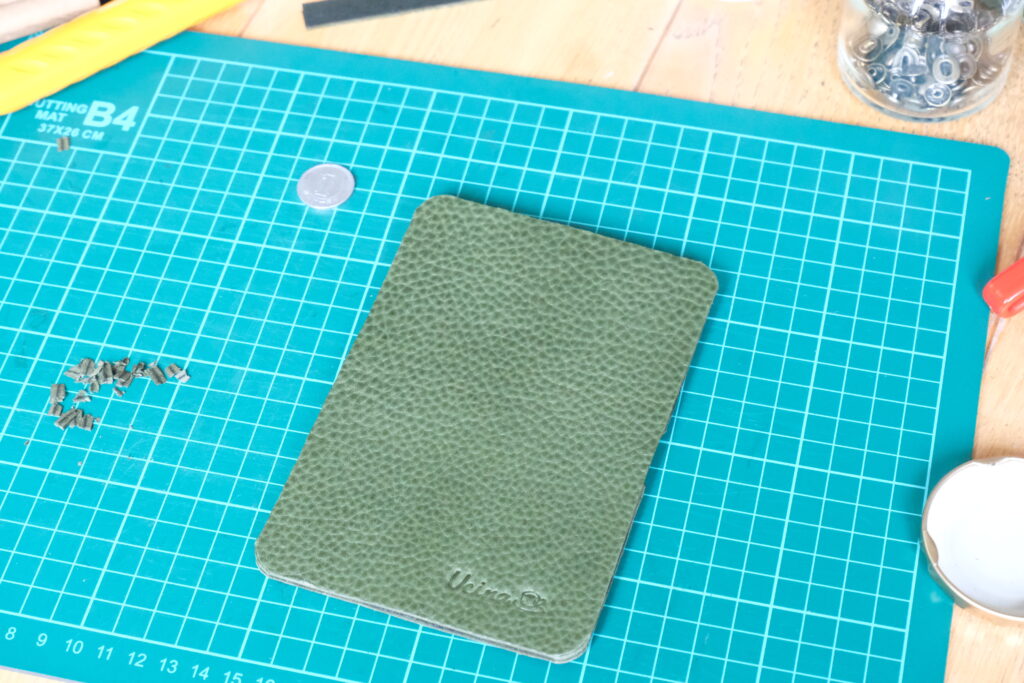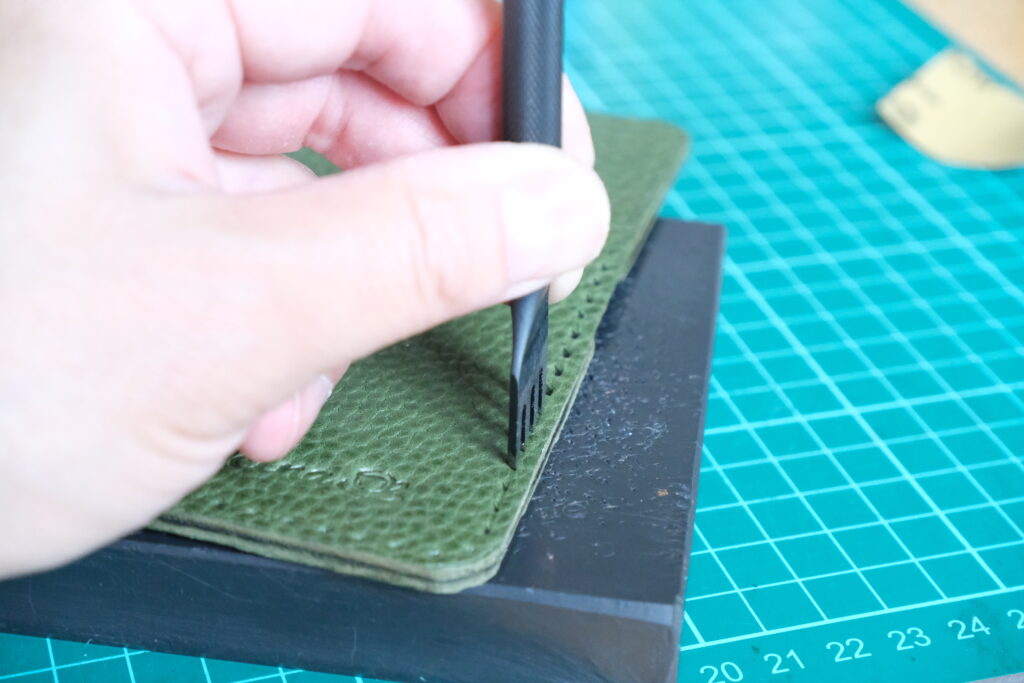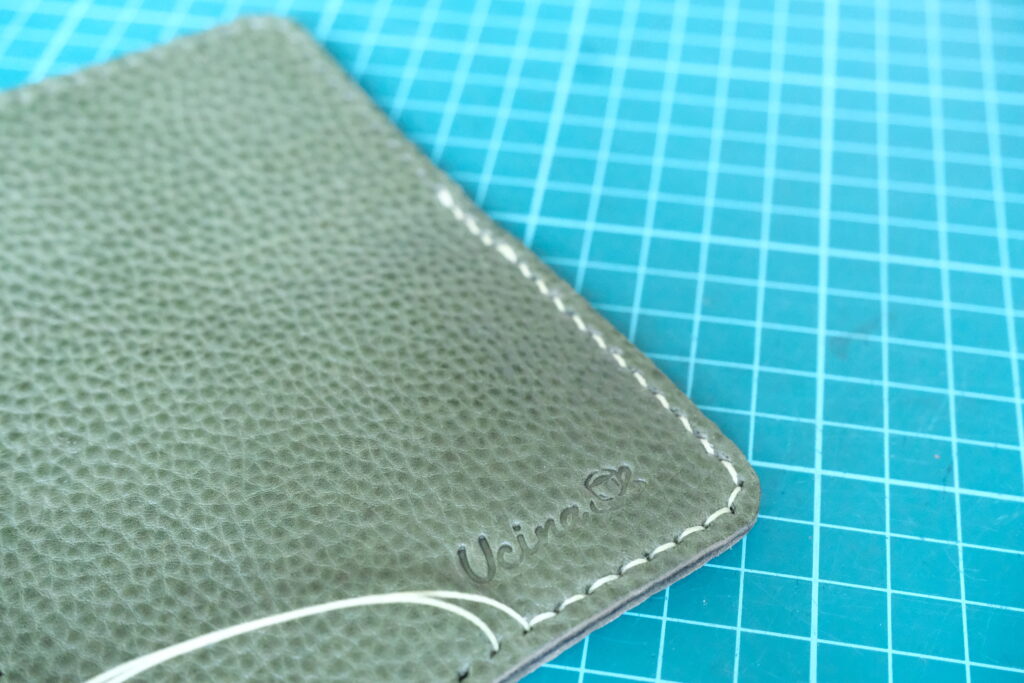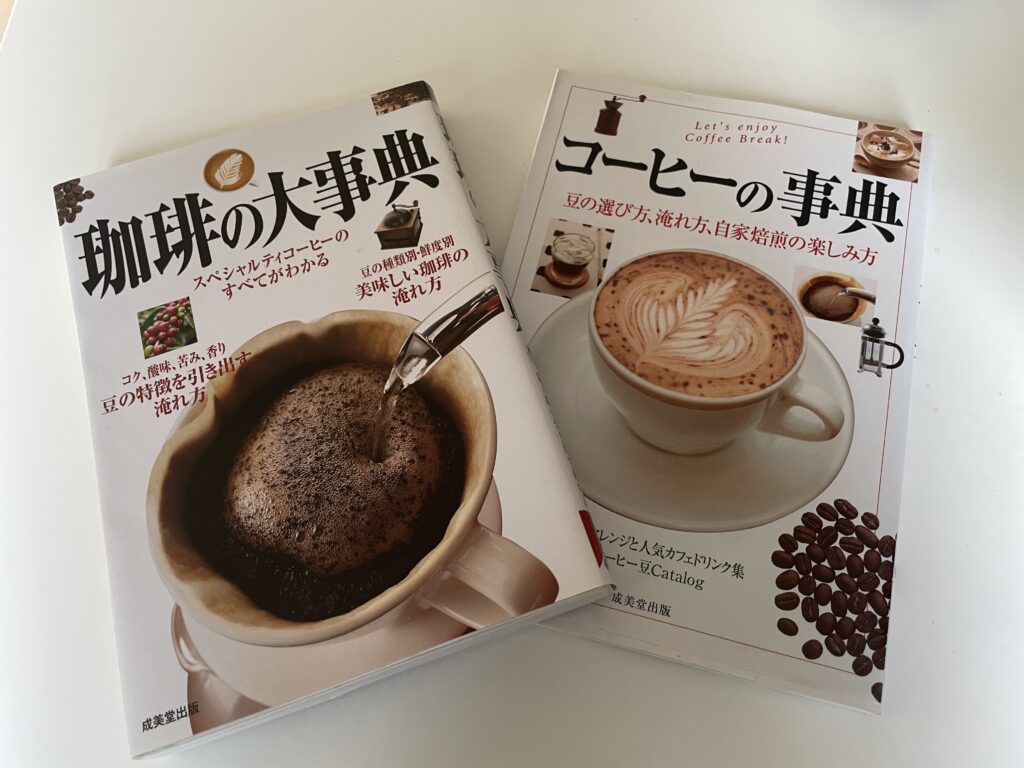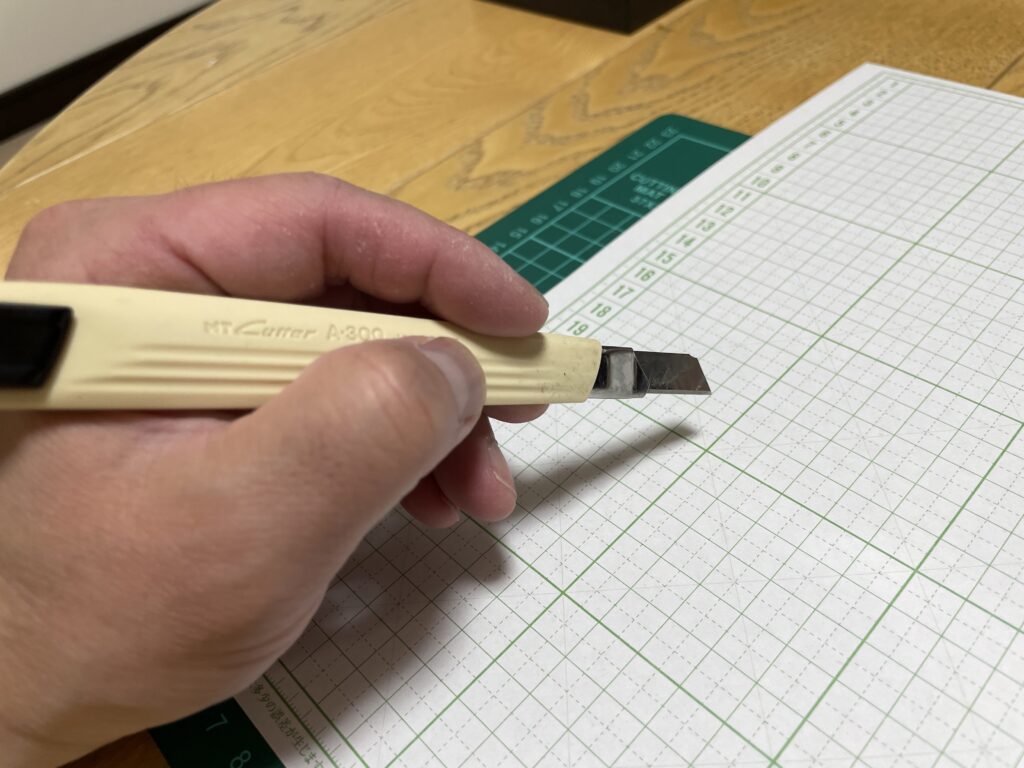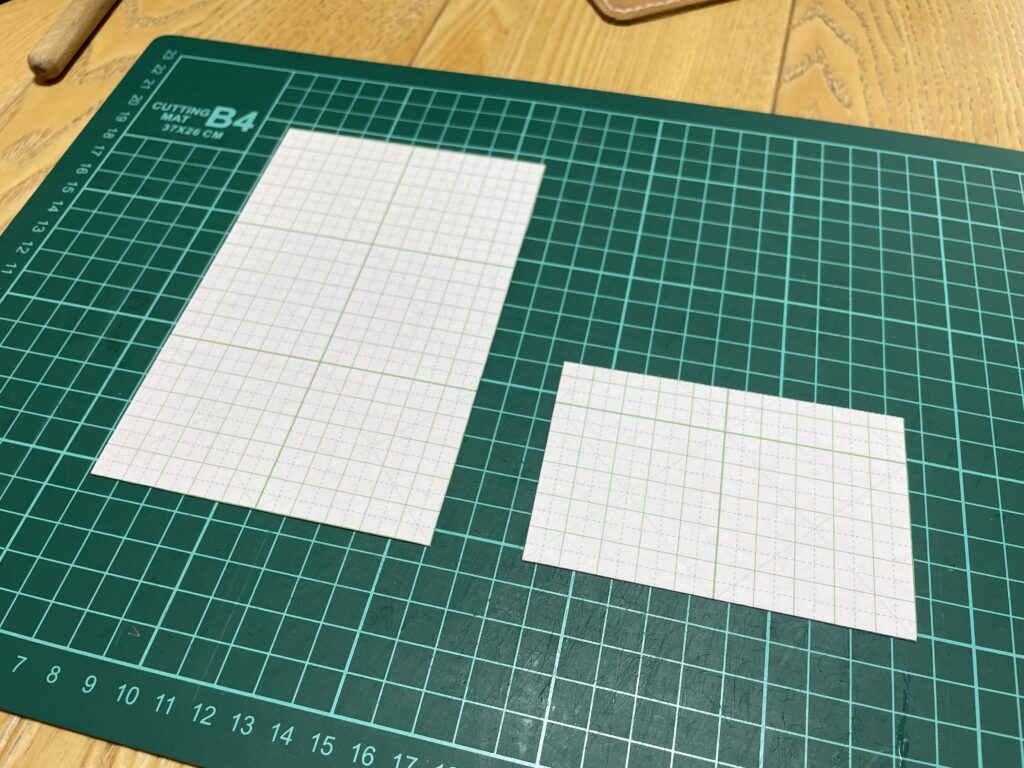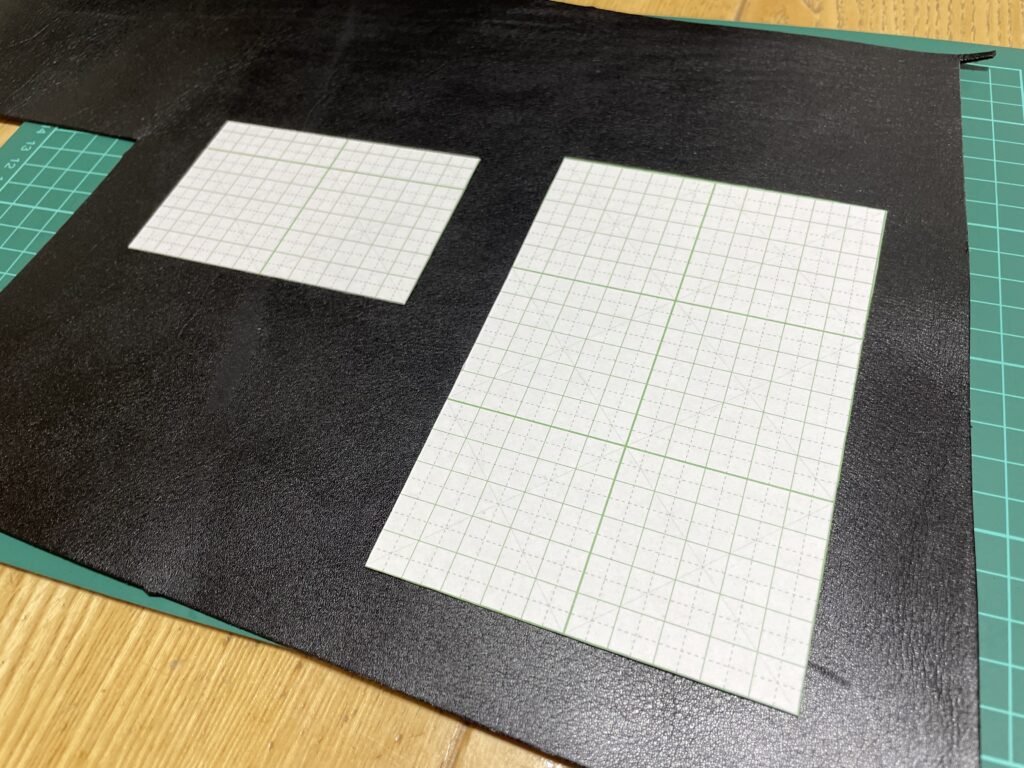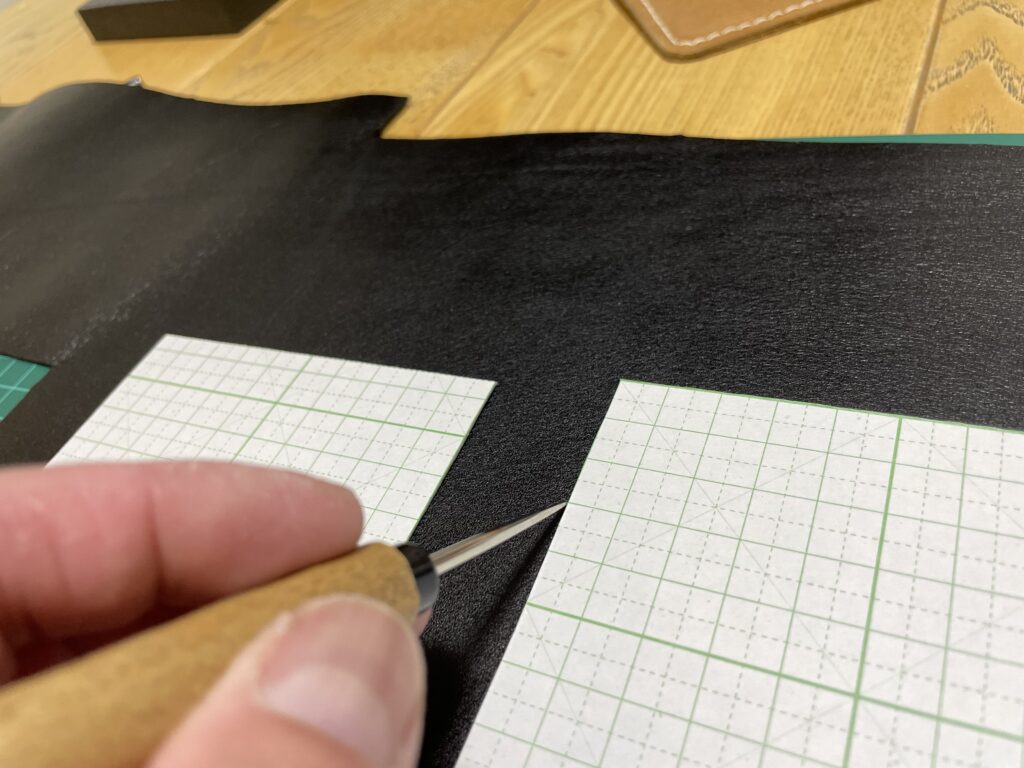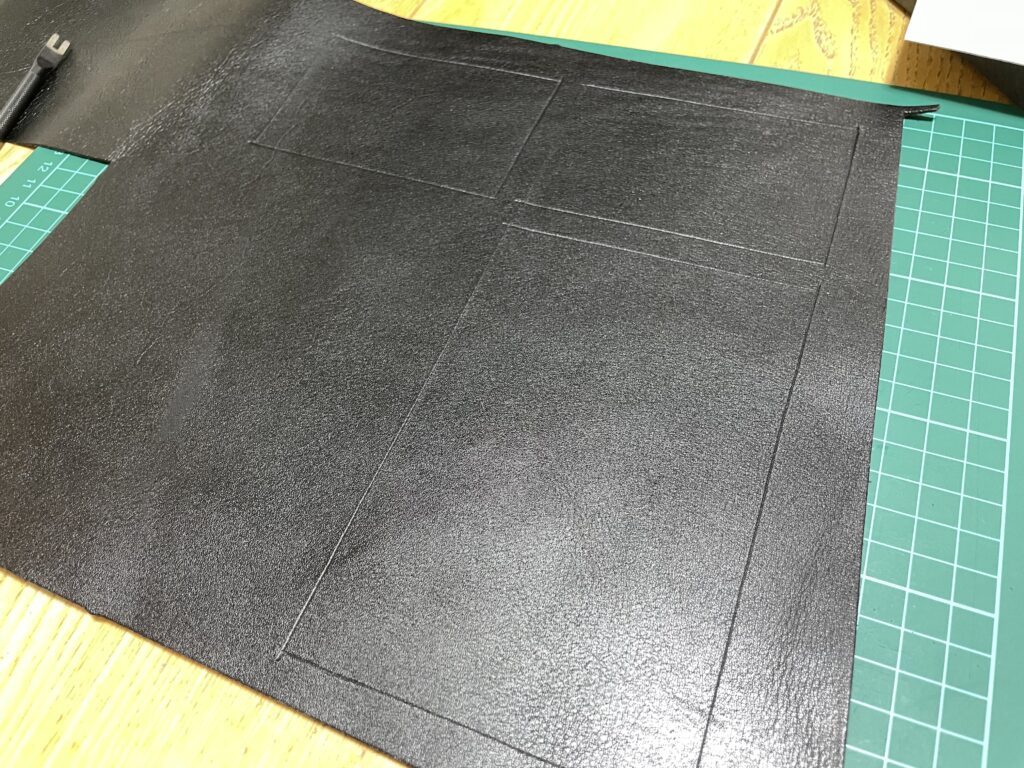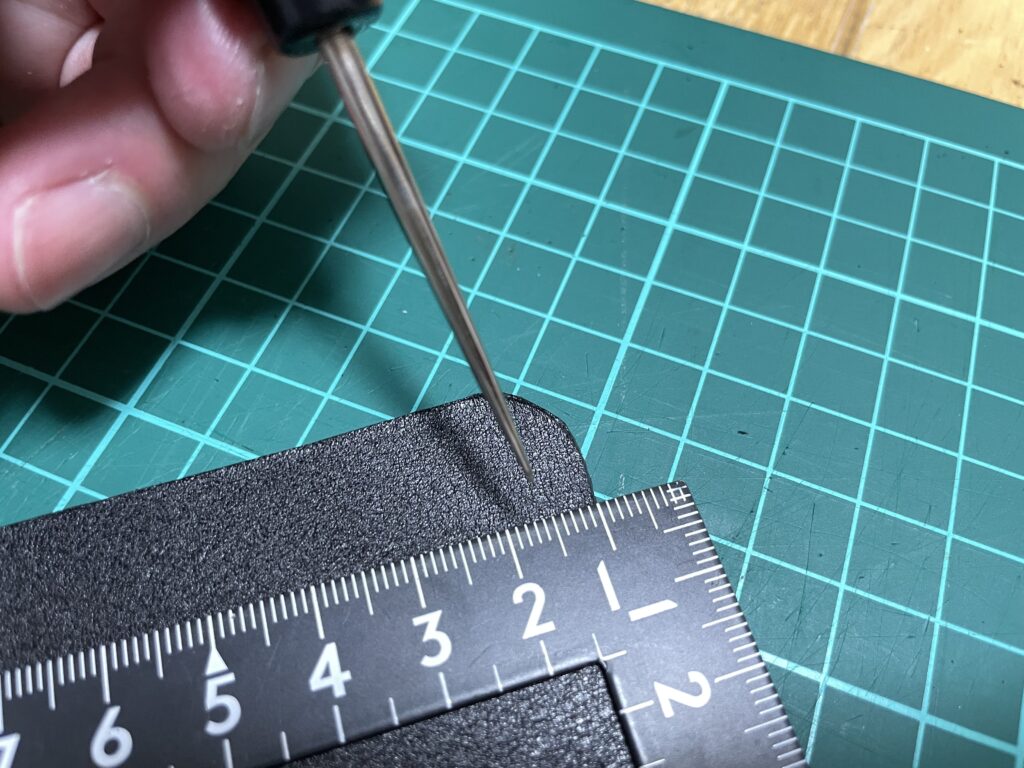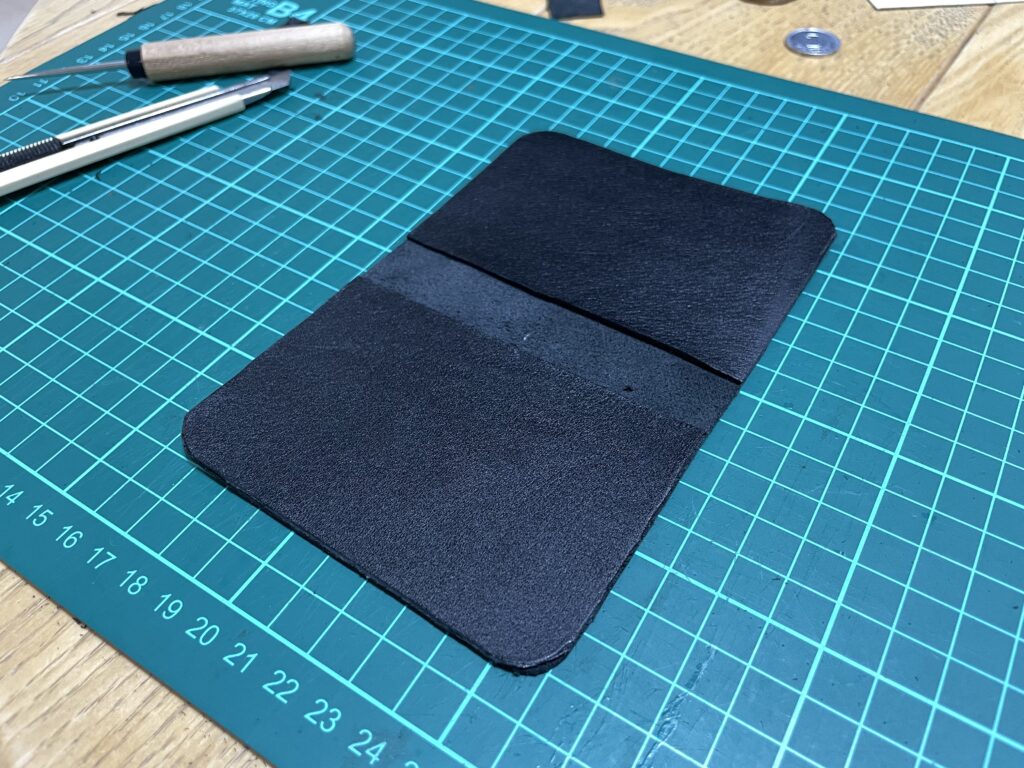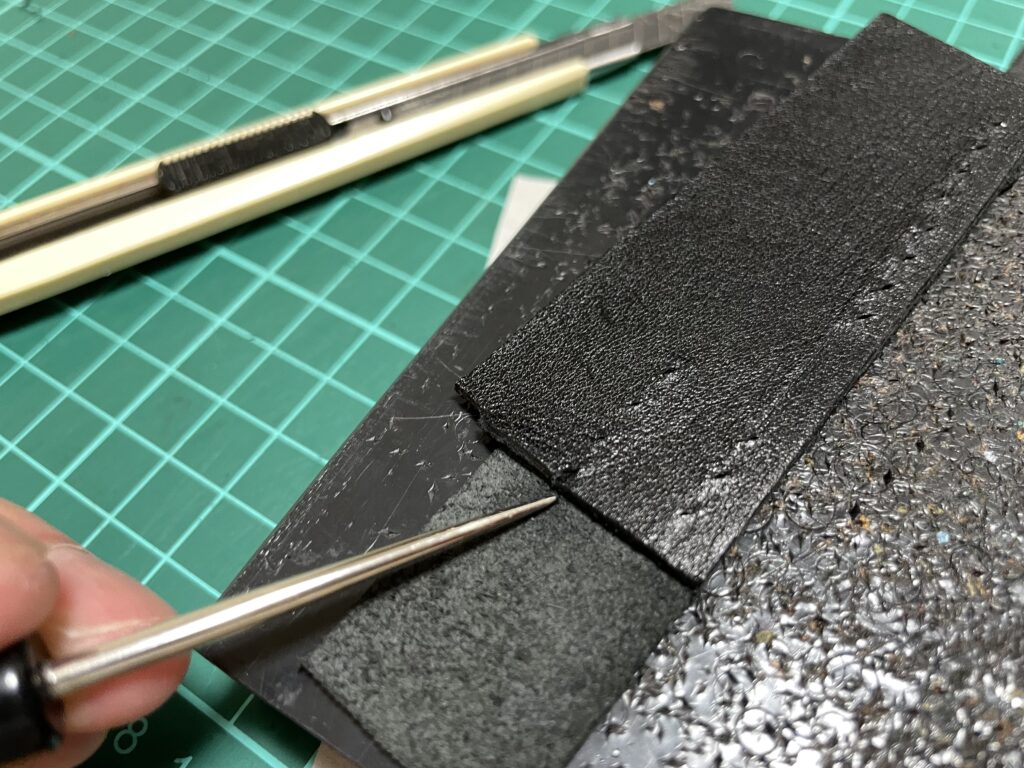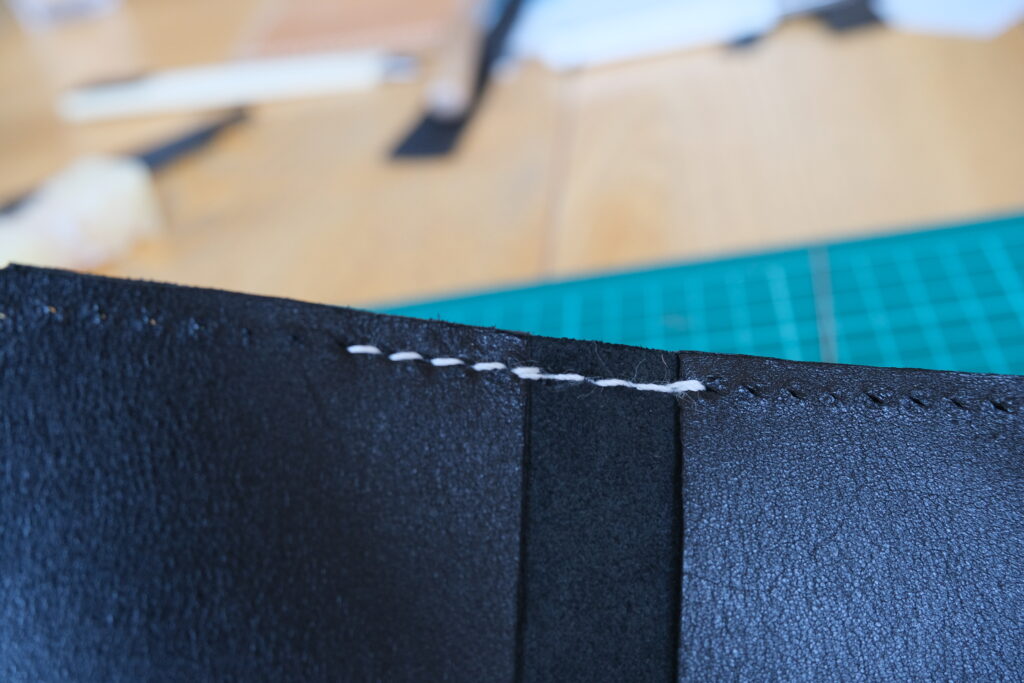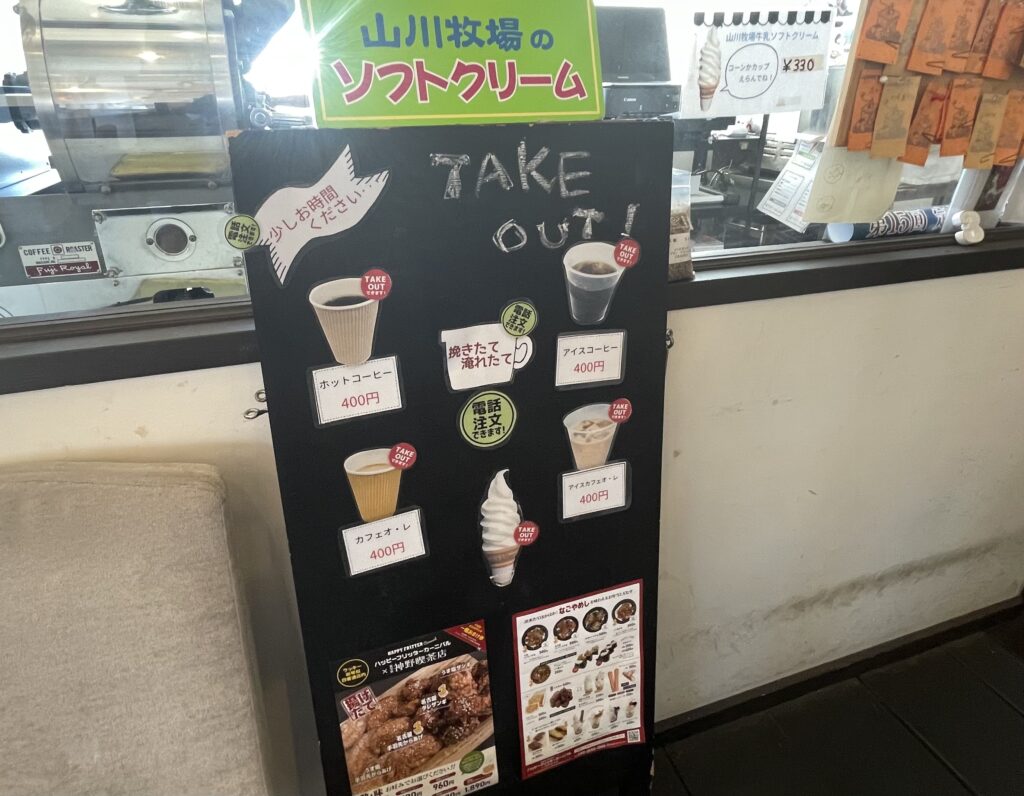珈琲を愛する皆様、こんにちは!
自家焙煎を始めてフライパン焙煎を何度か試してみて、
先日、手回し焙煎機、KALDI(カルディ)Coffee Roasterを購入!
今日は早速焙煎していきたいと思います。
手回し焙煎機によるコーヒーの自家焙煎
豆もいろいろ種類を買いましたが、
本日もブラジル サントス No.2でやってみます。
最大250gまでできると言うことで、250gでやってみます。
ハンドピックもしました。

道具を準備

コーヒーロースター設置
軍手、タイマーなどなど、
そしてチャフ問題のNewアイテム
KAKACOOコーヒークーラーを買いました!

冷却とチャフ受けがあって、色々調べてこれにしました。
そしてホッパーをロートとエルボで自作しました。


焙煎開始
先ずはコーヒーロースターを予熱します。
この温度計は精度がいまいちみたいなレビューもあったので参考値として
200℃まで上げて180℃まで下がったところで豆投入。

一人でやっているので写真撮る余裕がなく写真が減ります(笑)。
ここからひたすらぐるぐる回します。

火力が強すぎたか、6分30秒くらいで1ハゼがきてしまい、
そこから火力はだいぶ絞りましたが、2ハゼが9分30秒くらいでした。
11分くらいで煎り止めしました。
すぐに冷却。

あっと言う間に冷えます。
チャフも下のチャフ受けにしっかりたまります。

凄く良い感じ!
焙煎完了
無事、焙煎完了!
ちょっと時間は短くなってしまった気はするけど、
次の参考にしよう。
フライパン焙煎よりも、焼きムラも少なく
油分も出て良い色。

自作のホッパーの角度がきつ過ぎたせいで豆を入れるときに結構こぼしたのと、
やはり250gは多かったのかハゼの時に
焙煎機の口から豆が多少飛び出したので仕上がりが196gになりました。

思ったよりも仕上がりが良い感じ!
もちろん、置いた方が良いけど先ずは焙煎したてで飲んでみる。
中挽きで挽いて淹れてみます。




焙煎したてなのでめちゃめちゃ膨らみます。

飲んでみました。
酸味が少なく、苦すぎずまろやかな感じ。
なかなか好みの味。
楽しくて美味しかった!

終わりに反省点
反省点
・豆を入れる時にホッパーの中に豆が残っていて多少こぼしてしまった。
・そもそも豆の量が多かった、次は200gでやる。
・火力が強かった為か、豆を入れた後も極端に温度が下がらず、焼き上がりが早かった。
あと手回し焙煎機はコンロ回りがめっちゃ散らかります!
掃除までが焙煎です(笑)。

反省点を生かしてどんどん焙煎していこうと思います。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。